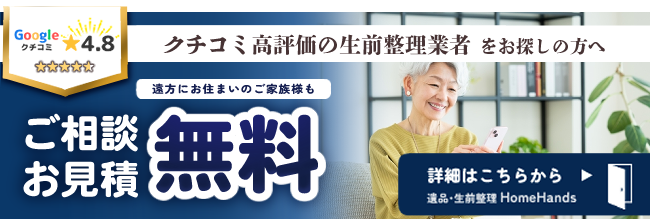「生前整理を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」と悩んでいませんか? 生前整理は、ただモノを捨てることではありません。ご自身の人生を振り返り、未来をより豊かにするための大切な準備です。
この記事では、生前整理をスムーズに進めるための第一歩、「モノの仕分け」について、具体的なコツをご紹介します。
仕分けの基本は「4つの分類」
生前整理のモノの仕分けは、まずすべてのモノを次の4つのカテゴリーに分けることから始めます。
- 必要なモノ(要):今後も日常生活で使うモノや、手元に残しておきたい大切なモノ。
- 不要なモノ(不要):もう使わないモノ、壊れているモノ、同じようなモノが複数ある場合など。
- 迷うモノ(保留):いますぐに「要る・要らない」の判断ができないモノ。
- 思い出のモノ(思い出):家族写真、手紙、記念品など、感情的な価値が高いモノ。
「要・不要」で判断できないモノは、無理に答えを出そうとせず、いったん「保留」にしましょう。無理に進めると挫折の原因になります。
【カテゴリー別】仕分けのポイント
1.「必要なモノ」を判断する
「このモノは、これからも自分や家族の役に立つか?」と問いかけてみましょう。
・日用品や家具:今使っているモノで、まだ使える状態のモノ
・貴重品:通帳、印鑑、年金手帳、保険証券、権利書など、生活に不可欠な書類
・思い出のモノ:毎日眺めたい写真や、大切にしたい手紙など
2.「不要なモノ」を見極める
「1年以上使っていないモノは、今後も使う可能性が低い」と考えてみましょう。
・古い衣類:流行遅れの服、サイズが合わなくなった服など
・壊れた家電や家具:修理する予定のないモノ
・重複しているモノ:いくつもある洗剤のストック、同じような調理器具など
・趣味を辞めたモノ:使わなくなったゴルフ道具やコレクションなど
3.「迷うモノ」は無理に決めない
「保留ボックス」を用意して、判断に迷うモノはすべてそこに入れましょう。
・「いつか使うかも…」と考えるモノ:いつか使う日は来ないことがほとんどです
・高価だったモノ:捨てるにもはもったいないと感じるモノ
・人からもらったモノ:相手に申し訳ないと感じるモノ
保留ボックスに入れたモノは、後日改めて見直す時間を設けます。時間をおくことで、冷静に判断できるようになります。
4.「思い出のモノ」は最後に
生前整理で一番時間がかかり、心労を伴うのが思い出のモノです。最初に取り掛かると、作業が中断してしまいがちです。
・無理に捨てようとしない:すべてのモノを捨てる必要はありません
・デジタル化も検討:大量の写真は、データに変換してコンパクトに保管する方法もあります
・家族に相談する:家族と一緒に、何を残すかを話し合ってみましょう
生前整理を始めるにあたって
生前整理は、ご自身の持ち物を整理するだけでなく、ご家族への負担を減らすことにも繋がります。焦らず、ご自身のペースで少しずつ進めることが大切です。
「どこから手をつけていいかわからない」「一人では進まない」という方は、プロの力を借りることも有効な手段です。私たち終活ホームハンズでは、お客様に寄り添い、丁寧なサポートを提供しています。いつでもお気軽にご相談ください。