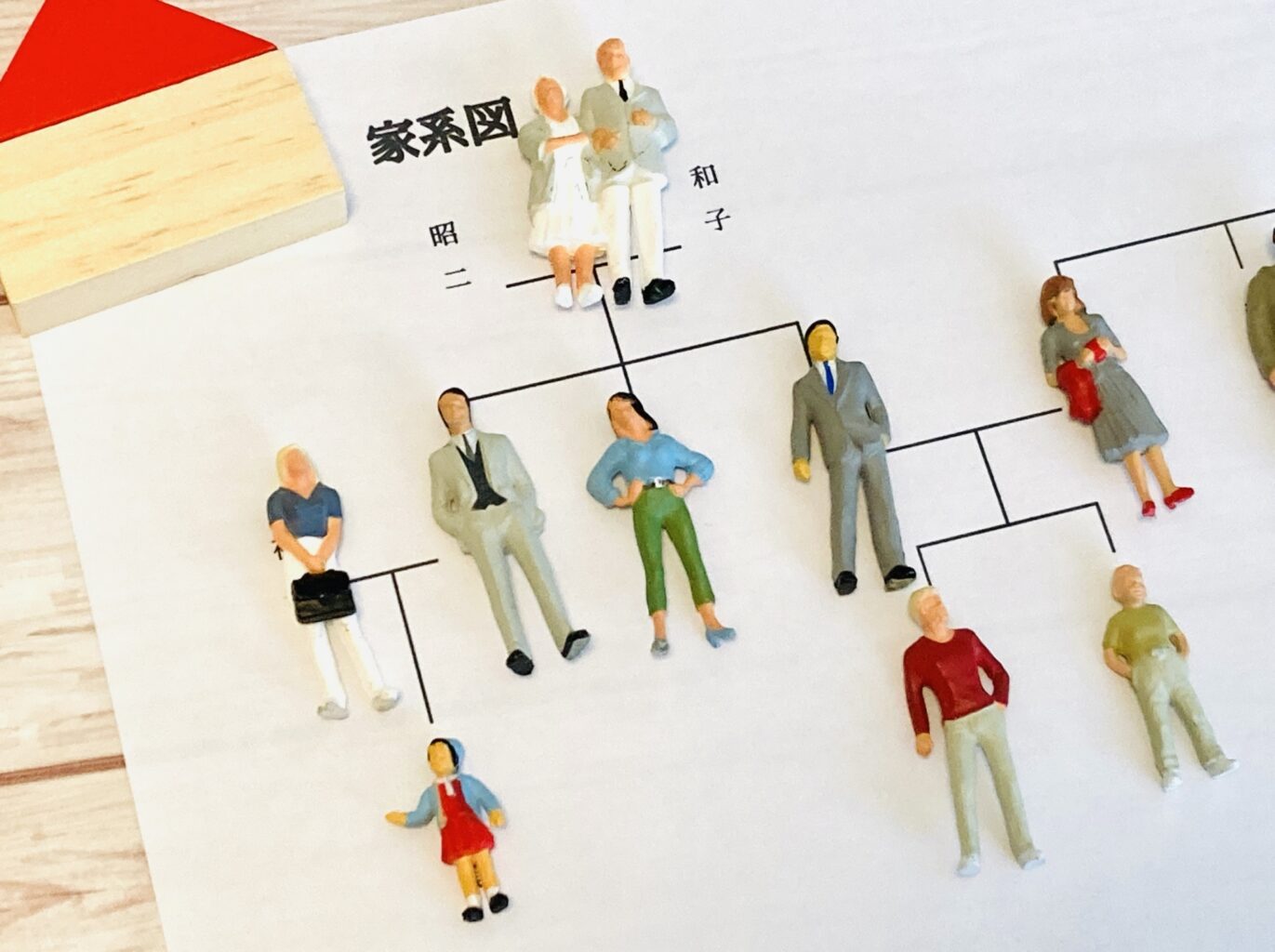
「まさか、自分が…」そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、少子高齢化や未婚化が進む現代において、相続人がいないという状況は決して他人事ではありません。もし、あなたに相続する人が誰もいなかった場合、あなたの残した大切な財産はどうなってしまうのでしょうか?
今回は、相続人がいない場合に起こること、そして、そうならないための生前対策について、終活の専門家である私たちが分かりやすく解説いたします。
相続人がいないとどうなる?~民法の規定~
民法では、相続人が一人もいない場合、最終的にあなたの財産は国のものになります(国庫に帰属といいます)。しかし、すぐに国のものになるわけではありません。そこには、法律で定められた手続きが存在します。
まず、家庭裁判所によって相続財産清算人という人が選任されます。この相続財産清算人は、あなたの財産を適切に管理し、清算するための役割を担います。具体的には、以下のような業務を行います。
- 相続人の捜索: 公告などを通じて、相続人がいないかどうかを調査します。
- 債権者・受遺者の捜索: あなたに財産を請求できる人(債権者)や、遺言によって財産を受け取るはずだった人(受遺者)を探します。
- 財産の管理・換価: 不動産や有価証券などを売却し、現金に換えるなど、財産を管理・処分します。
- 債務の弁済: 見つかった債権者に、あなたの財産から借金などを返済します。
特別な関係にあった人へ~特別縁故者への財産分与~
もし、法律上の相続人ではないけれど、あなたと特別な関係にあった人がいる場合、その人は家庭裁判所に特別縁故者としての財産分与を申し立てることができます。
特別縁故者として認められる可能性があるのは、例えば以下のようなケースです。
- 内縁の配偶者
- 生計を同じくしていた親族
- 療養看護に尽力した人
- その他、被相続人と特別の縁故があったと認められる人
ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所による審判が必要となり、必ずしも認められるとは限りません。
あなたの財産が国庫に帰属するまで
相続人の捜索期間(原則として公告後6ヶ月以上)、債権者・受遺者の捜索期間(原則として公告後2ヶ月以上)を経て、それでも相続人や受遺者が現れず、特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、最終的にあなたの残した財産は国庫に帰属することになります。
この手続きには相当な時間がかかり、その間、あなたの財産が積極的に活用されることは基本的にありません。
生前の備えが大切です
「自分の財産は、お世話になったあの人に遺したい」「長年活動してきた団体に役立ててほしい」そう考えるのであれば、生前の対策が非常に重要になります。主な対策としては、以下のものがあります。
- 遺言書の作成: 誰に、何を、どのように遺したいのかを明確に記した遺言書を作成することで、あなたの意思を確実に伝えることができます。
- 生前贈与: 生きているうちに、特定の個人や団体に財産を贈与する方法です。ただし、贈与税などの税金面を考慮する必要があります。
- 信託の活用: 信頼できる人に財産の管理・処分を託し、あなたの希望する形で財産を承継させる方法です。
- 生命保険の活用: 受取人を指定することで、相続とは異なる形で、特定の個人に保険金を渡すことができます。
これらの対策を行うことで、あなたの想いを大切な人に届け、財産を有効に活用してもらうことができるのです。
最後に
相続人がいないからといって、何も準備しないままでいると、自分の思いとは違う形で財産が処理されてしまうこともあります。
終活は、自分の人生の締めくくりを自ら設計する大切な機会です。将来の不安を減らし、安心して暮らしていくためにも、ぜひ一度専門家にご相談ください。



















